あつまってみる
セルフケアのために、できる範囲で。
私たちの動けなさ、出られなさ、申し訳なさ、働けなさ、生きづらさ……。
過去の自分のふるまいや現在の環境、何かの事故や災害めいたもの、家族や一族から押し付けられたもの、今の自分が抱えている特性、いろんなものが合わさって色んな意味での「動けなさ」が生まれている訳ですが、そうしたものに押しつぶされないように生きていくのに、独力で立ち向かうのはしんどいなぁと私たち、あるのメンバーは感じています。
私たちは支援の専門家ではないので、誰かに必要な医療・福祉的なもの(治療やケア、必要なサポート)をお渡しする組織ではありません。それでも、そうであってもいいから。自分が自分であるために、独りで時間を過ごしていくのではなく誰かと一緒に、何かお互いにとって良いことをする時間・空間を持とうと思いました。
藁にもすがるような、そこにいる人が誰であってもすがりついてしまうような、そんなフェーズからは脱したような気がするくらいには回復(リカバリー)の途上にはあって。でも今の現状をどうしたらいいか分からない。必要な支援が分からない、得られない、期待することにも疲れてきた。そんな人たちが、できる範囲でいいから自分で自分のためにできることをやってあげよう。
自分の抱えている「つらさ、できなさ、動けなさ」の渦中で生き、そうしたものをまず受け止めている「当事者」である自分のために、自分にできる範囲での自分へのいたわりであったり、提案であったりをしていってあげよう。そんな気持ちで行なっている活動です。
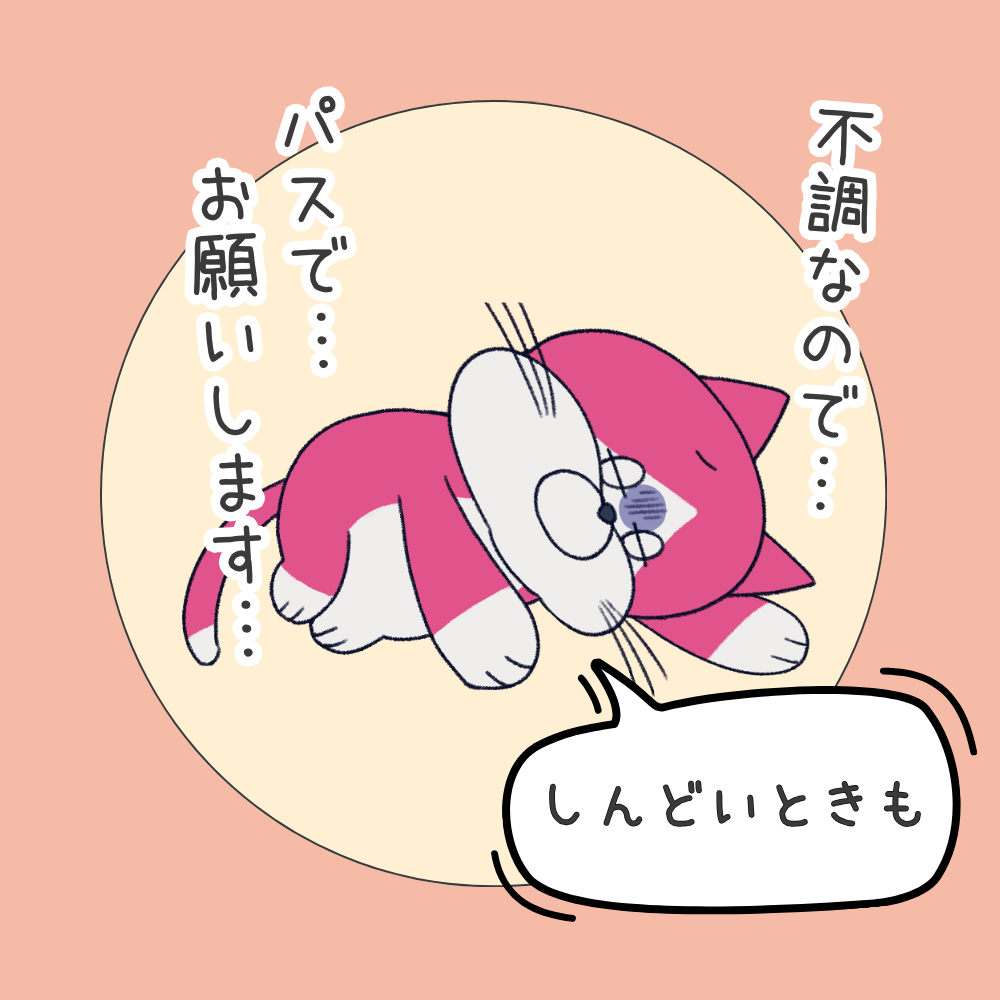
当事者研究
ーなかまと一緒に、苦労や困りごとを眺め自分のことを研究するー
自分自身の「できなさ」「生きづらさ」「こだわり」「とらわれ」などを題材に、その第一人者である自分が自分の責任において、その「できなさ」を研究してみる、というのが「当事者研究」です。日本では、2002年に北海道浦河町にある「べてるの家」という施設で始まった実践から広く取り上げられるようになった活動のようです。
浦河べてるの家,「べてるの家の『当事者研究』」,2005 https://www.igaku-shoin.co.jp/book/detail/10144
向谷地生良、浦河べてるの家,「安心して絶望できる人生」,2006 https://www.nhk-book.co.jp/detail/000000881992006.html
こうした支援の現場の実践、それも利用者発信から始まった取り組みですから、当団体の代表調べによると、「このやり方でなければ『当事者研究』とは言ってはいけない」という言説は見つからなかった、ということで私たちなりのプログラムを作ってみました。今は少しずつ手を加えたりしながら、自分たち向け、あるいはご依頼でおうかがいした先、どちらも同じ枠組みで実施しています。


自分たちで開催するときは、対面の集まり、あるいはオンラインの集まりとして実施しています。許可が取れた回など、当事者研究の実践報告はHPの活動報告にたびたび掲載しています。よければそちらもご覧ください、具体的なイメージがつかんでいただけると思います。
マインドフル・ヨガ
兵庫県西宮市の公民館を会場に、「医療法人内海慈仁会 有馬病院」さんのご協力の下、セルフケアのためのヨガプログラムを実施しています。
現在は月に1度、2時間のプログラムで開催しています。不定期ではありますがヨガの活動報告はある公式noteにてまとめています。よければご覧ください。

ご参加にあたって。会場のキャパシティと参加者同士の安全の確保、安心のための仕組みづくりとして、初めてのご参加の前にいちど、事前説明と見学参加をお願いしています。これは有馬病院さんとの協議の結果、ルール化したものです。ご協力お願いします。
興味・関心がおありの方は他の活動にご参加いただいたときなどに、メンバーにおたずねください。
その他 対面/オンラインの集まり
ー同じ時間、同じ空間を一緒に。ー
「当事者研究」の結果や、日々のコミュニケーションや気付きの中から、「集まってみる」活動は生まれては消え、消えては生まれて。対面あるいはオンラインで、他団体さんとの共催も含め、「居場所」性のある活動もやっています。
・作業はしたいけど1人では始められないというメンバーが、オンライン環境で「co-workingスペース(オンラインシェアオフィス)」を始めました。オンラインの活動に複数回、ご参加いただきアクセスができるようになった方向けに、法人でオンラインスペースを使ってない時間を活用して週に1,2度、ときに他団体と共催で開催しています。
・ボードゲームを使って、対人支援の現場でできるプログラムを開発したりして、ときどきご依頼にお呼ばれしたりしています。自分にできることで、何かできることはないだろうかと考えるのも「当事者研究」の一環なのかもしれません。
・一緒にお外を歩く「おさんぽの会」は寒くなると難しくなったので、活動自体が凍結中だったりします。こうして活動はなくなったりします。
・他団体との共催企画では、「お茶のマインドフルネス」ワークショップや、「手芸部」といった活動をやったりしています。
いろいろと広く開いて活動をしたいと思いつつ、告知・広報が後手に回っています。ゆっくり整備して、ゆっくり公開していきます。よろしくお願いします。

